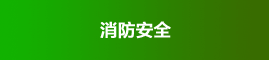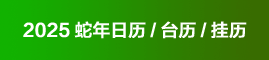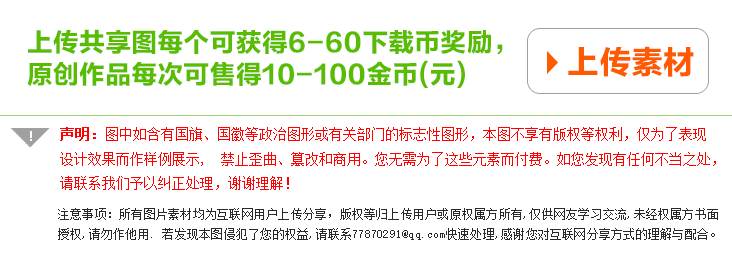本帖最后由 灵动江南 于 2014-4-6 17:28 编辑
资源素材内容: 仅含个别字。
「杉明朝体の制作コンセプト」杉本幸治
◇2000年の頃であったと記憶している。昔の三省堂明朝体が懐かしくなって、何とかこれを蘇らせることができないだろうかと思うようになった。
ちょうど「本明朝ファミリー」の制作と若干の補整などの作業は一段落していた。しかしながら、そのよりどころとなる三省堂明朝体の資料としては、原図は先の大戦で消失して、まったく皆無の状態であった。
わずかな資料は、戦前の三省堂版の教科書や印刷物などであったが、それらは全字種を網羅しているわけではない。したがって当時のパターン原版や、活字母型を彫刻する際に、実際に観察していた私の記憶にかろうじて留めているのに過ぎなかった。
◇戦前の三省堂明朝体は、世上から注目されていた「ベントン活字母型彫刻機」による最新鋭の活字母型制作法として高い評価を得ていた。この技法は精密な機械彫刻であったから、母型の深さ、即ち活字の高低差が揃っていて印刷ムラが無かった。加えて文字の画線部の字配りには均整がとれていて、電胎母型の明朝体とは比較にならなかった。
しかしながら、戦後になって活字母型や活字書体の話題が取り上げられるようになると、「三省堂明朝はベントンで彫られた書体だから、幾何学的で堅い表情をしている」とか、「理科学系の書籍向きで、文学的な書籍には向かない」とする評価もあった。確かに三省堂明朝体は堅くて鋭利な印象を与えていた。
しかし、それはベントンで彫られたからではなく、昭和初期の文字設計者、桑田福太郎と、その助手となった松橋勝二の発想と手法に基づく原図設計図によるものであったことはいうまでもない。
◇世評の一部には厳しいものもあったが、私は他社の書体と比べて、三省堂明朝体の文字の骨格、すなわち字配りや太さのバランスが優れていて、格調のある書体が好きだった。そんなこともあって、将来何らかの形でこの愛着を活用できればよいがという構想を温めていた。
三省堂在職時代の晩期に、別なテーマで、辞書組版と和欧混植における明朝活字の書体を様々な角度から考察した時、三省堂明朝でも太いし字面もやや大きすぎる、いうなれば、三省堂明朝の堅い表情、即ち硬筆調の雰囲気を活かし、縦横の画線の比率差を少なくした「極細明朝体」を作る構想が湧いた。
ちなみに既存の細明朝体をみると、確かに横線は細いが、その横線やはらいの始筆や終筆部に切れ字の現象があり、文字画線としては不明瞭な形象が多く、不安定さもあることに気づいた。そのような観点を踏まえて、全く新規の書体開発に取り組んだのが約10年前「杉本幸治の硬筆風極細新明朝」即ち今回の「杉明朝体」という書体が誕生する結果となった。
◇ひら仮名とカタ仮名の「両仮名」については、敢えて漢字と同じような硬筆風にはしなかった。仮名文字の形象は流麗な日本独自の歴史を背景としている。したがって無理に漢字とあわせて硬筆調にすると可読性に劣る結果を招く。既存の一般的な明朝体でも、仮名については毛筆調を採用するのと同様に、「杉明朝体」でも仮名の書風は軟調な雰囲気として、漢字と仮名のバランスに配慮した。
◇「杉明朝体」は極細明朝体の制作コンセプトをベースとして設計したところに主眼がある。したがって太さのウェートによるファミリー化の必要性は無いものとしている。一般的な風潮ではファミリー化を求めるが、太い書体の「勘亭流・寄席文字・相撲文字」には細いファミリーを持たないのと同様に考えている。
◇「杉明朝体」には多様な用途が考えられる。例えば金融市場の約款や、アクセントが無くて判別性に劣る細ゴシック体に代わる用途があるだろう。また、思いきって大きく使ってみたら、意外な紙面効果も期待できそうだ。
杉本幸治/1927年(昭和2)4月東京都台東区下谷うまれ。終戦直後1946年(昭和21)印刷・出版企業の株式会社三省堂入社。本文用明朝体、ゴシック体、辞書用の特殊書体などの設計開発と、ベントン機械式活字母型彫刻システムの管理に従事し、書体研究室、技術課長代理、植字製版課長を歴任。またその間、晃文堂(現・株式会社リョービイマジクス)の明朝体、ゴシック体の開発に際して援助を重ねた。「本明朝体」の制作を本格的に開始し、以来30数年余にわたって「本明朝ファミリー」の開発と監修に従事した。そしてこの度「杉明朝体」を開発した。「タイポデザインアーツ」主宰。 |